
大学院に通うか迷っているんですが、だいたい学費ってどれぐらい必要ですか?大学院でも奨学金があるって聞いたんですけど…
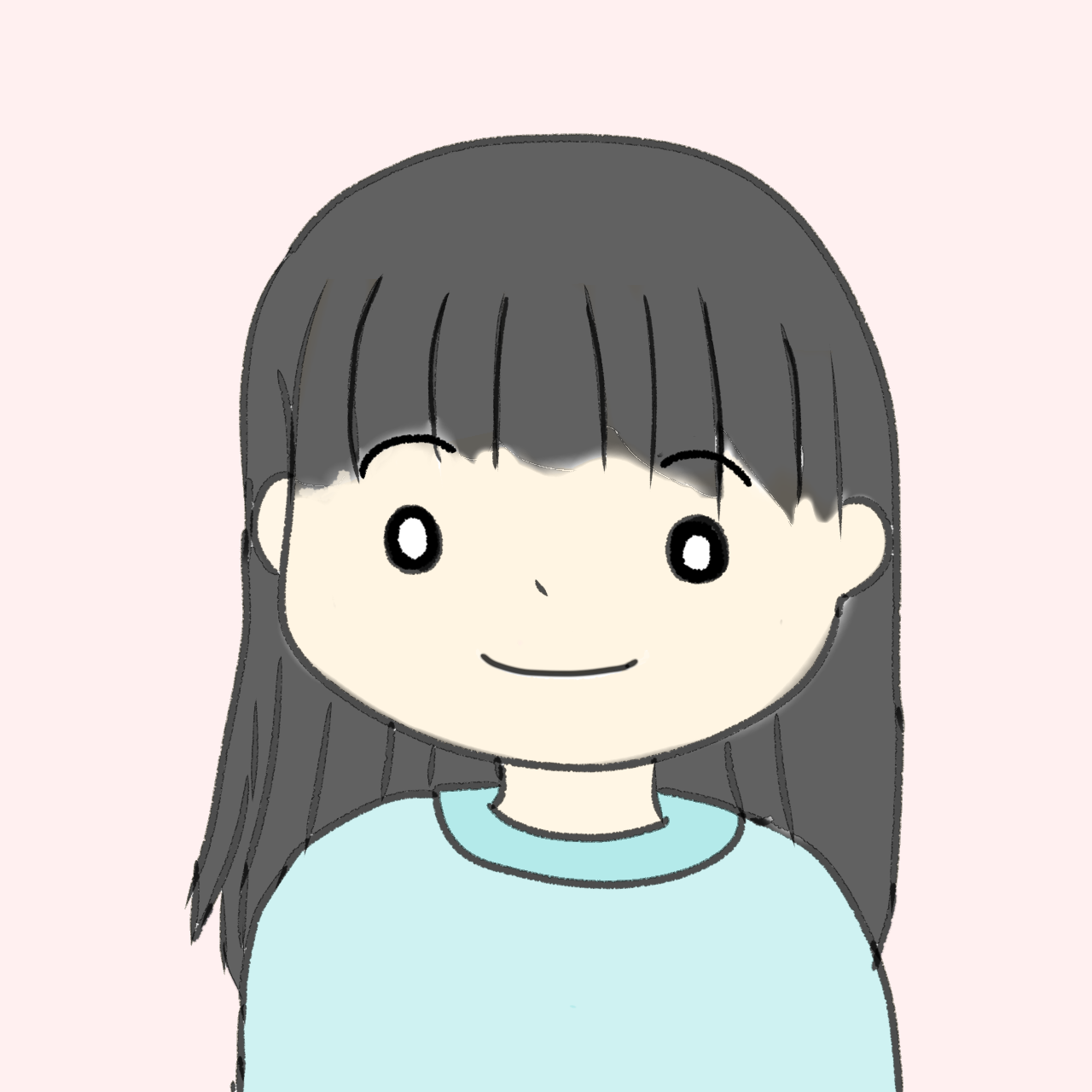
学費は私立か国公立かで全然違います。私の場合は…
こんにちは、日本語教師のさじここです。
大学院進学の壁に「学費」問題があると思います。
進学を躊躇している理由の一つになっているのではないでしょうか?
この記事では、大学院の学費、奨学金について取り上げたいと思います。
- 大学院に進学したいけど、学費が心配…
- 修士2年間でいくらぐらいかかるのか知りたい
- これから大学院に入学するので奨学金制度について知りたい
そんな方はぜひ最後までお読みいただければと思います。
- 大学院修士課程2年間分の大まかな学費(国立、私立の場合)
- 奨学金について
私は某国立大の修士課程に入学し、企業に勤めていたころの貯金で学費を工面しました。
私の場合、奨学金は結婚し主人の所得があったため対象外。
私立大は「学費が高すぎて自分には払えん!」と思い受験すらしていません。
でも最近、大学院の奨学金についての質問があって色々調べていたら、「こんなのあったの!? 知らなかった!」ということが……
これから進学を目指す方、入学される方が「知識不足で損をしないように」、また、進学を学費面で躊躇している方へのアドバイスも含めて私が調べたことをシェアしたいと思います。
ここでお伝えする情報は2022年2月10日現在のものです。
場合によっては、学費や奨学金制度が変更されたりしている可能性がありますので、必ずリソースの情報をご自身でもお確かめください。
大学院の学費

以前の投稿、大学院進学のデメリットでもお伝えしましたが、大学院の学費は国公立大学と私大では学費が全然違います。
例えば、国立大の場合…
一方、私立大の場合は…
修士2年間といえど、かなり高いですよね…😥
自分の貯金やアルバイト等だけではちょっと支払いが厳しい人もいらっしゃるかも…
特に一人暮らしで一人で生計を立てている方は経済的に大変になるかもしれません。
学費だけでなく、毎日の生活費や住居費、Wi-Fiなどの通信量、光熱費など…普通に生活するだけでもお金はかかります。
学費は払えても、毎日長時間アルバイトしないと生活できない!となると、進学しても学業との両立に悩むかもしれません😥
そういう経済的に支援が必要な方に向けて「奨学金」というものがあります。
奨学金について

一口に奨学金といっても、返還義務のある「貸与型」と、返還義務のない「給付型」があります。
応募資格・支援内容は様々なので、ご自身の状況に合わせて探すことが大切です。
ここでは私が調べた奨学金の共通のポイントを紹介します。
- ①申込みは大学院を通して行われる場合が多い
- ②奨学金の募集時期は、例年3〜5月(特に4月下旬まで)に集中する
- ③貸与奨学金の選考の多くは、学力基準&家計基準(所得制限)がある
- ④場合によっては、学内選考や指導教官の推薦状が必要になる
- ⑤奨学生採用時には健康診断書が必要になる可能性がある
このポイントを読んでいただくとわかるように、奨学金はだれでも簡単に借りられるというものではありません。
学内選考を突破したりや学力基準を満たさないと奨学生にはなれませんし、私のように生計を一緒にしている家族の収入があると所得制限にひっかかり対象外になる場合が多いです。
また、②で書いたとおり、奨学金の募集は大学院入学してすぐにあります!!
奨学金を考えている方は必ず、合格通知とともに送られてくる資料や大学院入学式で配布される資料などを細かくチェックしてアンテナを張っておかないと、いつの間にか募集が終わっていた…😱なんてことになりますので、ご注意ください!
私の大学院では入学式で配布される資料のなかに奨学金の申し込み案内が入っていました。
でも、時間割や履修登録資料、授業シラバス、生協の案内等…たくさんの資料と一緒になっていたため読まずに完全スルーしてしまいました😱
入学直後は頭の中が「履修登録」でいっぱいになると思いますが頭の片隅に「奨学金」のことを置いておきましょう!!😅
④で書いた「学内選考」について補足すると、学内選考で⼤学からの推薦が決まっても、推薦=採⽤決定というわけではないです。
その後 財団での選考があり、書類選考のほか⾯接がある場合もありますので、財団やその財団の ⺟体の企業等のこと、奨学⾦がなぜ必要でどのように使⽤するか、⾃⼰ PR、⾃分の将来、⾃ 分の研究(特に⼤学院⽣)等について充分に考え、準備をしたうえで申請しなくてはいけません。
それを突破してやっと奨学生になれます。
まるで、就活みたいですよね…😅
まあ、お金を借りたりもらったりするわけですから当然といっちゃ当然ですが……
日本学生支援機構の奨学金
この「日本学生支援機構の奨学金」は有名でおそらく各大学HP(奨学金のところ)でも触れられているかと思います。
この奨学金制度のは基本「貸与型」ですが、特に優れた業績を挙げた人は返済免除になる可能性があります。以下、日本学生支援機構からの引用です。
大学院で第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、貸与期間中に特に優れた業績を挙げた者として日本学生支援機構が認定した人を対象に、その奨学金の全額または半額を返還免除する制度です。
学問分野での顕著な成果や発明・発見のほか、専攻分野に関する文化・芸術・スポーツにおけるめざましい活躍、ボランティア等での顕著な社会貢献等も含めて評価し、学生の学修へのインセンティブ向上を目的としています。
貸与終了時に大学に申請し、大学長から推薦された人を対象として、本機構の業績優秀者奨学金返還免除認定委員会の審議を経て決定されます。
日本学生支援機構 HP「特に優れた業績による返還免除の手続き」よりhttps://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/gyosekimenjo/index.html (2022年2月11日閲覧)
第一種奨学金の家計基準
日本学生支援機構の奨学金の返済免除を受けるには、「第一種奨学金」の対象になる必要があります。
第一種奨学金の対象になるには以下の家計基準に当てはまらなければなりません。
本人の収入(定職、アルバイト、父母等からの給付、奨学金、その他の収入により本人が1年間に得た金額)と配偶者の定職収入の金額の合計額が、下記の金額以下の場合、選考の対象となります。配偶者が給与所得者の場合は、配偶者のみ下表の給与所得控除をしたうえで、本人の収入金額と合算します。なお、定職収入が給与所得以外の場合は、収入金額から必要経費を控除した額となります。
引用:日本学生支援機構HP「進学前(予約採用)の第一種奨学金の家計基準」より〈https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/kakei/yoyaku.html〉(2022年2月11日)
表1:<収入基準額>
| 修士・博士前期課程・専門職大学院(法科大学院を含む) | 299万円(※389万円) |
|---|---|
| 博士後期課程・博士医・歯・獣医・薬(6年制学部卒)学課程 | 340万円(※442万円) |
※研究能力が特に優れている者、特別な事情があると認められる者などについての収入基準超過額の許容範囲
表2:<配偶者の給与所得控除額について>
| 年間収入金額(税込) | 控除額 |
|---|---|
| 268万円未満 | 年間収入金額と同額 |
| 268万円を超えて400万円以下 | 年間収入金額×0.2+214万円 |
| 400万円を超えて781万円以下 | 年間収入金額×0.3+174万円 |
| 781万円を超える場合 | 408万円 |
つまり、独身の場合、年間収入が299万円以下だったら、申請ができます(表1)。
配偶者がいる場合は、{(配偶者の年間の収入)ー(控除額の金額(表2))}+自分の収入を計算し、収入基準額が299万円以下だったら申請できます。
業績の評価基準
業績の評価基準についてはざっくり説明するとこんな感じ↓です。
- 学位論文その他の研究論文が教授会での高い評価,関連した研究内容の学会での発表,学術雑誌への掲載又は表彰等,当該論文の内容が特に優れていると認められた
- 研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められた
- 専攻分野に関連した著書,データベースその他の著作物等が社会的に高い評価を受けるなど,特に優れた活動実績として評価された
- 特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められた
- 授業科目の成績が教授会等で高く評価され優秀な成績を挙げたと認められた
- 研究又は教育に係る補助業務で教育研究活動に大きく貢献し,かつ特に優れた業績を挙げたと認められた
- 音楽,演劇,美術その他芸術の発表会における成績で特に優秀な成績を挙げたと認められた
- スポーツの競技会における成績で特に優秀な成績を挙げたと認められた
- ボランティア活動その他の社会貢献活動で社会的に高い評価を受ける等,公益の増進に寄与した研究業績であると評価された
参照:日本学生支援機構HP「特に優れた業績と評価方法」https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/gyosekimenjo/hyoka.html〈2022年2月11日閲覧〉
この条件を読むと、相当頑張らないと難しいことが分かるかと思います😥
個人的に気になる点として「教授会」による判断が多いことです。
大学の規模によって所属する教授の人数、院生の人数にともなう厳しさ異なるので、大学によってはかなりハードルが高いかもしれません……
それでも頑張りたいという方は、学会誌への論文投稿や海外の学会での発表、投稿を目指してみましょう!
最近は特に海外の学会誌への投稿掲載はポイントが高いと思いますので、英語で論文を書くのをおすすめします。(こんなことを言っている私はそんな能力はありません…😅)
その他の奨学金

奨学金は上記以外にも調べれば色んなものがあります。
日本証券奨学財団の奨学金
「日本証券奨学財団」の奨学金は、
- 専攻分野に制約はない
- 奨学金の返済義務はない(給付型)
- 学業修了後の進路は自由
- 月額45 ,000円(自宅外通学者は55,000円)
- 採用予定数…60名程度
- 指定大学の大学生に限る
日本証券奨学財団 HPより 〈https://jssf.or.jp/scholarship.html〉(2022年2月11日閲覧)
あまり制約のない奨学金じゃないかと思います。
以下の指定大学の学生で、大学からの推薦を受けることができれば選考にエントリーできます。
<指定大学>
北海道、東北、新潟、筑波、お茶の⽔⼥⼦、東京、東京⼯業、⼀橋、東京都⽴、慶應義塾、上智、中央、⽇本、法政、明治、⽴教、早稲⽥、横浜国⽴、名古屋、名古屋市⽴、京都、同志社、⽴命館、⼤阪、⼤阪市⽴、関⻄、神⼾、関⻄学院、広島、九州
日本証券奨学財団 HPより 〈https://jssf.or.jp/scholarship.html〉(2022年2月11日閲覧)
興味がある方は、上記の日本証券奨学財団のHPで確認ください!
本庄国際奨学財団
「本庄国際奨学財団」の奨学金は、
- 返済の義務がない(給付型)
- 支給額:月額20万を1〜2年間 / 月額18万を3年間 / 月額15万円を4〜5年間
- 国際学会への出席費用も支給される
- 奨学金受給中は他の奨学金との併用不可、アルバイトも禁止(TAなど研究に関するものや通訳、国際交流の手伝いなどは除く)
- 奨学金受給中は年4回面談があり、その他行事等の参加義務がある
- 大学院修了後も同窓会などへの参加が求められる
- 採用予定人数…若干名
本庄国際奨学財団 HPより〈https://www.hisf.or.jp/scholarship/graduate-school/〉(2022年2月12日閲覧)
ただし、修士課程は30歳までに入学していることが条件です!
興味がある方は、本庄国際奨学財団のHPをご覧ください。
奨学金について調べられる便利なサイト
全部の奨学金についてはこの記事では書ききれないので、ぜひご自身で奨学金について調べてみてください。
奨学金についてわかりやすくまとまっているサイト↓を見つけましたのでシェアします。
奨学金.net →https://xn--kus49bd41h.net/
こちらのサイトは返さなくてもいい給付型の奨学金が紹介されていますので、おすすめです。
また、進学予定の大学院のHPには必ず奨学金の案内のページがあると思います。
まずはそのサイトを見て大学院と提携している奨学金を探してみるのがいいかもしれません。
大学院によって奨学金の力の入れ方が異なります。
他大学のHPも見てみると有益な情報が載っている可能性もありますので、チェックしてみてください。
奨学金の中には地域限定のものや、特定の大学、学部、研究限定のもの等もありますので、必ず募集案内を確認しましょう!!
奨学金の落とし穴…
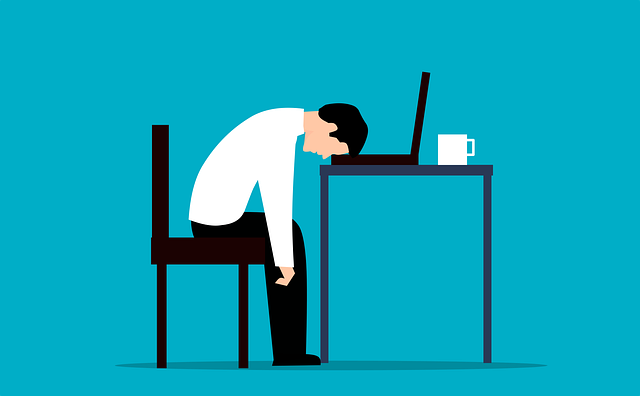
先述しましたが、奨学金は「貸与型」と「給付型」があります。
貸与型の場合、大学院を卒業したら返済義務がある…「借金」です!
今、大学学部進学でも問題になっている「奨学金:貸与型」
卒業後、借りた額をちゃんと返済できるのかも利用するかどうかの重要なポイントになると思います。
じゃあ、「給付型」に応募しよう!と思うかもしれませんが、「給付型」の奨学金のほうがもちろん難易度が高いでしょう。
そりゃみんなもらえるほうがいいですから、必然的に倍率が高くなり、選考が厳しくなります。
募集予定人数も若干名のところが多いです。
また、上記で紹介した「本庄国際奨学財団」の奨学金のように、奨学金受給中はアルバイトを禁止するという制約があるものもあります。
受給資格を得て「やっぱ受給を取り下げたい!」となっても簡単に取り下げることはできないので、よくよく考えて応募しましょう!
(選考には大学院側も絡んでいますから、取り下げるとなるといろいろ面倒なことになると思います😥)
まとめ

この記事では大学院2年間の学費と奨学金について紹介しました。
上記を読んでお分かりかと思いますが、決して誰でも簡単に返済義務のない給付型の奨学生になれるというわけではありません。
大学院生のほうが学部生よりも奨学生になりやすいという意見も見かけますが、私の周囲の日本人の院生を見る限り、簡単ではなさそうです。
(ただし、留学生の場合は別で、募集している奨学金がたくさんあり、日本人よりも奨学生になりやすいみたいです)
大学院に通った私の見解としては、できれば奨学金を当てにせずに貯金など自力で学費を工面することをおすすめします。
奨学金ありで学費の支払いを考えていると、万が一奨学生になれなかったとき大きなダメージが…😥
アルバイトをがむしゃらにして学業がおろそかになってしまったら「何のために大学院に行ってるの?」となってしまうかもしれません。
これから大学院を目指す人の中には、「大学院って授業が少ないから自由時間って結構あるでしょ?」と思っている方いるかもしれません。
でも、実際は毎日忙しくあっというv間に時間が過ぎていきます😅
2年で修論を完成させ、就活する人はしなくてはならない、教育実習があるとその期間は授業準備に追われる……思うようにアルバイトのシフトが入れられないかもしれません。
なので、余裕をもって大学院生活を送るためにも入学前にある程度、学費の貯金をしておきましょう!
奨学金の給付型はもらえたらラッキー程度に思っている方が気が楽になると思います。
そして、個人的には「貸与型」の奨学金は借りないほうがいいと思っています。
借金はなるべく作らないほうが身のためです。
「貯金がないから学費を自分だけで工面できない」という方は、お金を無理までして大学院に通う必要があるのか?を自問自答し、今一度立ち止まって考えてみてください。
大学院は何歳になっても通えます。
本当にやりたい研究に集中できる環境が整うまで、焦らず準備することも大切かと思います。
すみません、最後はちょっと説教みたいになってしまいました…😥
でも、私の周りに奨学金が返済できずに悩んでいる人がいたのでお伝えしました。
この記事はいろんなサイトを参考にして書いていますが、情報が古かったり間違った情報を載せてしまっているかもしれませんので、その際はご一報いただけると助かります。
この記事がこれから大学院を目指す方、進学する方のお役に立ったら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
「この情報が役に立った!」という方は「ブログ村」ボタン↓をクリックしていただけると嬉しいです😃
にほんブログ村


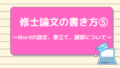
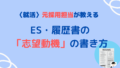
コメント